





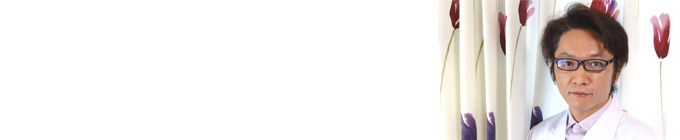
幼少期トラウマの影響:なぜ0〜3歳頃の期間は大切か?〜
原因不明のお悩みをお抱えの方へ

1.発達心理学の本等で解説されていますが、
分かり易いので、転載します。
■3歳頃までの成長期間はなぜ大切か?
赤ちゃんの頃には、養育者からのマザーリング(お母さんのような愛情とスキンシップで接すること)を受けることで、育ててくれる人への信頼を感じ、自分自身や自分が生きる世界も信頼できるものだという「基本的信頼感」を獲得します。
さらに1〜2歳頃になった子どもたちは、興味をひかれたものを見よう、触れようと外の世界に歩きだしていきますが、同時にそれまで密着していた養育者から離れていく「分離不安」を強く感じるようになります。そんなとき、養育者からいつでも温かく見守られ、不安な気持ちを「大丈夫」にかえてもらうことができれば、分離不安を乗り越え、集団生活の中に溶け込んでいくことができるのです。
■3歳頃までの育児を誤ると……?
この3歳頃までの欲求や不安に対して、養育者からの十分な対応がなされずにいると、どうなるでしょう?
赤ちゃんは、自分が送ったサイン(泣く、ぐずる、笑うなど)に対して応えてもらえないと、他者や自分を取り巻く世界への不信感を持ち、自分自身のことも、信じることができなくなってしまいます。この不信感は、その後の人生における対人関係や社会生活にも、色濃く影響していきます。
また、1〜2歳の頃に養育者との分離不安が残ると、その不安感をその後の人生で信頼を寄せた人(友だち、教師、恋人、上司など)との関係で表出していきます。一定の関係に必要以上に密着したがり、「私だけを見てほしい」「離れないでいてほしい」と束縛したくなります。少しでも心の距離を感じると、たまらなく不安で孤独に感じてしまいます。この対人関係における極端な不安感を、「見捨てられ不安」と言います。
3歳頃までの子の心の発達には、子どもをいつくしみ、安全基地となるような「お母さん的なかかわり」は、欠かせないものなのです。
たとえ専業主婦でも、育児ストレスでいつもイライラしていたり、家事や下の子の世話で忙しく、かまってあげられなかったりすると、やはり子どもの心には不信感や不安、寂しさが残ってしまいます。
ワーキングマザーの場合はどうでしょう? 保育園などを利用していれば、保育士が母親に代わってお母さん的なかかわりをしてくれます。とはいえ、子どもが成長するベースは何と言っても家庭です。
家庭でやすらぎや安心を得られない、お母さん的なかかわりを得られない、ベビーシッターなど養育者が目まぐるしく変わる、といった環境で過ごすと、そこで育った人の心には、やはり不信感や不安、寂しさが残ってしまいます。
以上。
All About より 抜粋転載。
幼少期がいかに大切かという事が分かりますね。
まとめると
「基本的信頼感」を獲得できなかった場合、
「分離不安」を乗り越えられなかった場合、
*他者や自分を取り巻く世界への不信感を持ち、
自分自身のことも信じることができなくなってしまいます。
*この不信感は、その後の人生における対人関係や社会生活にも、
色濃く影響していきます。
*不安感をその後の人生で信頼を寄せた人
友だち、
教師、
恋人、
上司等
との関係で表れます。
一定の関係に必要以上に密着したがり、
「私だけを見てほしい」
「離れないでいてほしい」と束縛したくなります。
恋愛依存や、極端に人を束縛してしまう、
されるのを好む事につながっていきます。
なので、
幼少期に受けた心の傷が、
人間関係での悩みや、
鬱や、
依存等
につながることもあります。
幼少期の心の深い深い傷なので、
原因の発見がご自身では不可能な為、
例として、
「原因が分からないけど・・・人間関係で悩みが絶えない・・・・」
等と言う事が起こります。
心の深い深い傷なので、
カウンセリングだけで改善するのは難しいこともあるでしょう。
カウンセリングでは届かない深い領域にある心の傷を癒すには、
催眠療法が最適です。
(催眠療法によるトラウマの克服,治療,解消ついてはこちらをクリック{タップ})。
幼少期〜のトラウマはその時の(過去の)自分を知り、癒す(許す)事で、
トラウマから解放されるのです。

カウンセリングや催眠療法についての質問等ございましたら、
お気軽にご相談ください。
埼玉 カウンセリング&ヒーリングと催眠療法、
認知行動療法。
パニック障害、トラウマ克服
対面や通話で各種悩みの改善。
埼玉県草加市
総合セラピー・ルーム「 ヒーリング・スウィート」
認定心理カウンセラー
総合セラピスト 栗原 涼





